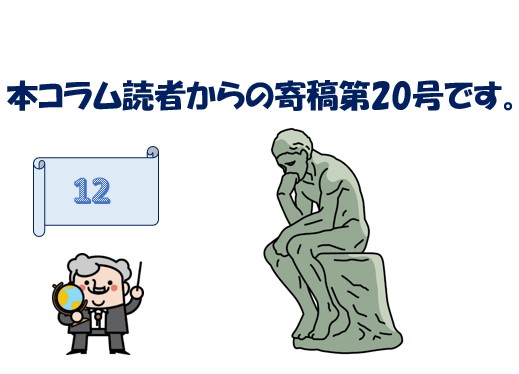
<2022.10.2寄稿> 寄稿者 たぬきち
1960年1月4日、『ペスト』『異邦人』の著者カミユは自動車事故死。車中の鞄から未完の原稿『最初の人間』(七久保敏彦 訳・新潮文庫)が見つかった。第1次大戦でアルジェリアからフランスの戦場に出て戦死した父、母と祖母の苦労、貧困の中での自分の成長と学業。無名の親のもとに生まれた子は、みな「最初の人間」、その親も「最初の人間」。だが、母から生まれた以上、「だれも最初の人間ではない」という。
社会の大きな困難と向き合う人生の実相は、そのままカミユの強さと弱さの人間味を示している。完成原稿でないだけでなく、カミユを批判したサルトルを頂点に左翼知識人の全盛期でもあり、その出版には1994年まで、34年も待たねばならなかった(サルトルは、1980年死去)。たちまちベストセラーとなったのは、やはり時代が変わり、革命や暴力よりも人間らしさが求められる社会が到来していたからだろう。
私自身は、1977年7月に旧西ドイツに留学し、そのまま「ドイツの秋(ドイツ赤軍77年攻勢。今でもそう呼ばれる)」を迎えてしまった。4月の検事総長に続き、7月ドレスナー銀行頭取の殺害、9月の経団連会長誘拐(運転手・護衛4名射殺)、10月パレスチナ過激派によるルフトハンザ機ハイジャック。機長の遺体を滑走路に投げ捨て、シュライヤー経団連会長とシュタムハイム刑務所に収監されている赤軍幹部達の交換を要求したが、失敗するとアンドレアス・バーダーをはじめとする囚人は一斉自殺(国家による殺人という主張も)。シュライヤー会長は処刑された。
私は、当時のヘルムート・シュミット首相(SPD=社民党)の地元ハンブルクにいたが、市民は『これは戦争なのだ』と異口同音に言っていた。驚いたのは、哲学者サルトルが刑務所にバーダーを訪ねたという1974年のニュースだった。『世界のサルトル』がパリから面会に赴くだけで、強力な支援となったであろう。1972年のミュンヘンオリンピックで、パレスチナのテロ組織『黒い9月』が11名のイスラエル人選手を殺害したときも、サルトルは『選手全員が軍人だった』と、これを支持したと知り、さらに驚いた(東京五輪での黙祷や、ドイツ大統領による警備の不手際への謝罪などが、いま行われている)。
「実存哲学」を唱えるサルトルの「アンガージュモン(社会参加)」は、マルクス主義と革命、反植民地・反米・反帝国主義で、そのためなら極端な暴力も容認するものだった。ソ連を称賛し、その強制収容所の存在を認めず、カストロとゲバラ、毛沢東、イラン革命前のホメイニにもボーヴォワールと面談に赴き、彼らの人格をたたえた。アルジェリア戦争では、もちろん独立派を支持し、にえきらないカミユを追及した。
カンボジアの虐殺者ポル・ポトは、若い頃パリに留学して知った『黒い皮膚・白い仮面』(海老坂=加藤 訳・みすず書房)の著者でマルチニク出身の黒人精神科医フランツ・ファノンの反植民地・暴力肯定に触発されたという。だがファノンは、最後の著作『地に呪われたる者』(浦野=鈴木 訳・同)にサルトルが寄せた序文の「暴力と殺人」奨励に、「本文で私はそんなことを言ってない!」と驚いたものの、白血病で急逝(未亡人が出版社へ、序文の表現を和らげてほしいと求めたが、「一人のヨーロッパ人をほうむることは一石二鳥」というサルトルの言葉は、そのまま)。
パリ解放後の1945年、対独協力紙の編集長35歳のロベール・ブラジャックが銃殺刑に処されることになったとき、「言論活動だけで死刑とは」と、多くの知識人が立場の違いを超え助命嘆願に署名した。サルトルとボーヴォワールは頑としてこれに応じず、「言論で人を死に追いやった者は、死刑で当然」と主張(オンフレ『リバタリアン秩序』フラマリオン[仏語])。『シャルル・ドゴール』や『知識人の時代』の著者ミシェル・ヴィノックは、「サルトルはいつも間違っていたのか?」という(https://www.diplomatie.gouv.fr/)。
1979年、サルトルは、ベトナムの「ボート・ピープル」救済をジスカール・デスタン大統領に直訴した。1975年のベトナム戦争終結で生じた難民だが、いまフランスでは地中海の「ボート・ピープル」を助けるのに、「サルトルいでよ」と言われている。だが、彼のこの行為は、最晩年に珍しく「まいた種を刈る」ものだったのではないだろうか。
1966年9月、サルトルとボーヴォワールが来日。羽田到着時の記者会見で、サルトルは、「若い頃に教員として日本に来ることを願ったのだが採用されなかった」、「ようやく青年時代の夢がかなった」と、打ち明けている(三田評論)。その真情の吐露(とろ)には好感が持てる。
彼は、1938年最初の長編小説『嘔吐(おうと)』(白井浩司 訳・人文書院)のなかに、訪れたこともない「釜石」を登場させた。「眼を閉じさえすれば」、「裸かになって樽の中でからだを洗っていたカマイシ(釜石)のひとりの日本の女」、「などを、頭の中に見ることができた」(白井浩司 訳・人文書院)。その理由として「カマイシという音が美しいから」と話している(松田十刻『遙かなるカマイシ』もりおか文庫)。
コロナ禍で、カミユの『ペスト』(疫病でなく、ナチズムの暗喩とも)が、いま世界中で読まれているという。次に読んでほしいのは、『最初の人間』である。サルトルにしても、当初の希望がかない教師として日本に居着いていたならばと、思わずにおれない。