

<2022.1.16記>
私がある自主管理のマンション(ハイツN)の管理組合で理事長をしており、その管理運営で日々悪戦苦闘していることはコラム№76(止水)で述べているが、当該マンションが築40年を迎えるに当たり、理事長としてある決断をした。

<2022.1.6記>
不動産には沢山の「価格」の呼称が存在する。公的な価格と言えば、「路線価」「公示価格」「基準地価」「固定資産税評価額」が挙げられるが、それらの特色を要領良く理解するには、①調査主体、②調査時点、③公表時期、④主たる目的・用途、の4項目に絞って覚えておくと良いと思う。探究心旺盛な方は、路線価の(角地・奥行等)の補正率に至るまで気になってしまうと思うが、実務では大まかな「考え方」を体系的に把握しておくことをお勧めする。

<2021.12.1記>
稀なことではあるが、心ない分譲マンションの原設計を目の当たりにし、その「配慮の無さ」に苛立ち、分譲主の「利益至上主義」の思惑までもが透けて見えたような気がして憤りを覚えることがある。

<2021.11.13記>
ある家賃保証会社(以下「保証会社」)の督促部隊は警備員と見紛う制服で昼夜問わず都心部を駆け回っている。

<2021.10.14記>
私が興味本位で出席した管理組合の定期総会での一幕である。(「興味本位」と言葉は悪いが当社は「棚卸資産(販売用不動産)」の総会議案に関しては原則「中立」の姿勢ということ。)議案が「管理費・修繕積立金の値上げ」の審議に入るや否や、その若き投資家と思しき青年は真っ先に挙手して朗々と反対意見を述べた。

<2021.9.1記>
コラム№104の「細分化」は、単に不動産の「空間(=区画形質の変更)」によるものを述べている。しかしながら、不動産には「時」を刻む、即ち「使用時間」を細分化することによっても流動性を高め、より大きな利益を追求できる経営手法が数多く存在する。

<2021.8.16記>
不動産のスケールメリット創出の最たるものは「再開発」だと思う。今回のコラムは、前々回のコラム№104「細分化」と対照的なテーマになるが、不動産は「細分化」とは真逆の「集約・統合」の方がより高度な付加価値が生み出される傾向があることを述べたい。

<2021.8.2記>
その痛ましい事件が発覚したのは2011年の年始めである。大阪府豊中市で60歳代の姉妹がマンションの一室で極度に痩せ細った変死体で発見された。

<2021.7.14記>
不動産の細分化の最たるものは区分所有マンションだと思う。50億円のマンションを一括して購入できる個人はそういないと思うが、都心部で平均価格5,000万円のファミリータイプ100戸なら然程難しい分譲事業ではない。

<2021.5.1記>
随分昔の話であるが、販売図面を見て思わず吹き出してしまったことがある。「リフォーム要!」とセールスポイントと見紛うばかりの大文字で書いてあるのが衝撃的だったからだ。
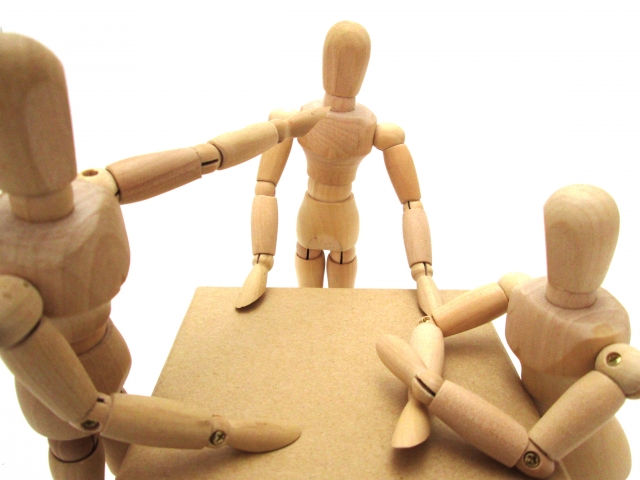
<2021.4.14記>
「バブル経済」の余韻がまだ残る平成の初めの頃、見識を疑う販売(促進)資料を目の当たりにして「苦言」を呈したことがある。(本コラムは、前回のコラム№97「インフレ」の後編)

<2021.4.1記>
誰もが不動産を「持つリスク」にも「持たざるリスク」にも晒されている。原因は、インフレーション(=inflation、通貨膨張、以下「インフレ」)とデフレーション(=Deflation、物価収縮、以下「デフレ」)である。